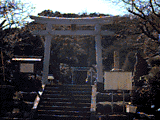
走水神社は日本武尊、涕橘姫命がまつられていますが、涕橘姫命は本来、旗山崎(走水港の先端)の橘神社に祭られていました。明治42年にここが軍用地となった為に、現在の走水神社に移されました。
走水神社そのものの建設記録は亨保年間の火災で消失していますが、伝説では景行天皇即位40年の東洟征討で日本武尊が千葉に渡るときに走水で村民に「冠」を賜わり、それを石櫃に入れ、社殿を設けたと言われています。
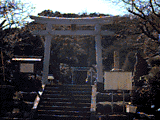 |
走水の地名は、古くは古事記(712)、日本書紀(720)に出てきており、大和朝廷時代には、千葉を経て東北に至る「古東海道」が通っていました。 走水神社は日本武尊、涕橘姫命がまつられていますが、涕橘姫命は本来、旗山崎(走水港の先端)の橘神社に祭られていました。明治42年にここが軍用地となった為に、現在の走水神社に移されました。 走水神社そのものの建設記録は亨保年間の火災で消失していますが、伝説では景行天皇即位40年の東洟征討で日本武尊が千葉に渡るときに走水で村民に「冠」を賜わり、それを石櫃に入れ、社殿を設けたと言われています。 |
|
日本武尊が千葉に渡ろうとしたときに、嵐がおこり、千葉に渡れないばかりか、遭難しかけました。この時、涕橘姫命が「さねさし さがむのをぬに もゆるひのはなかにたちて とひしきみはも」と歌い、海に身を投じ、海を静めました。 これにちなみ、明治43年、東郷平八郎、乃木希典等7名士により「橘の歌碑」が社殿の奥に立てられました。 また、社殿に上がる階段の右側には、昭和50年の国際婦人年に航海の安全を願って「舵の碑」を建てました。左側には、日本武尊に料理を献上した記念と包丁への感謝を表わすために昭和48年に走水の住民(大伴黒主)よって「包丁塚」が立てられています。 「舵の碑」の隣には「針の碑」が建てられており、針供養として「針の感謝祭」が行われます。 |
 |
| 包丁塚 | 橘の歌碑 | 舵の碑 | 針の碑 |
|---|---|---|---|
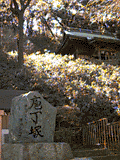 |
 |
 |
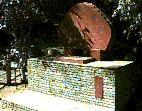 |
| 97.3.16 11:00 | 針の碑感謝祭 |
|---|